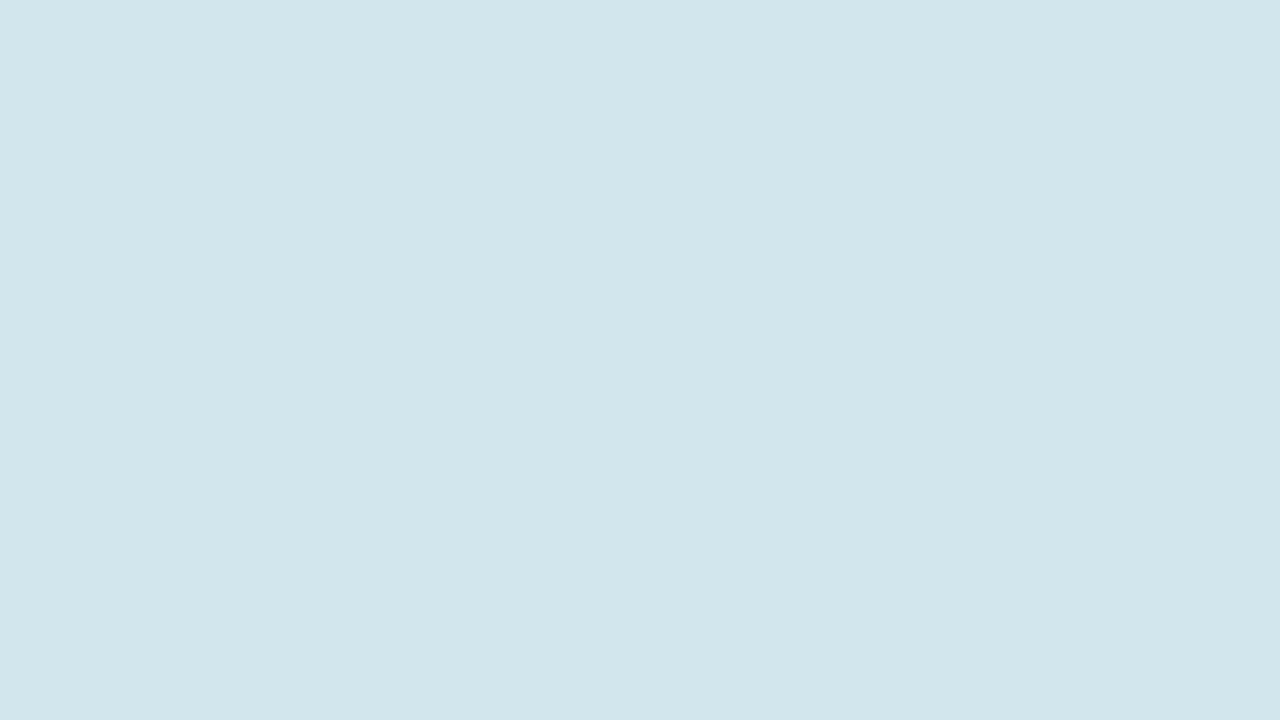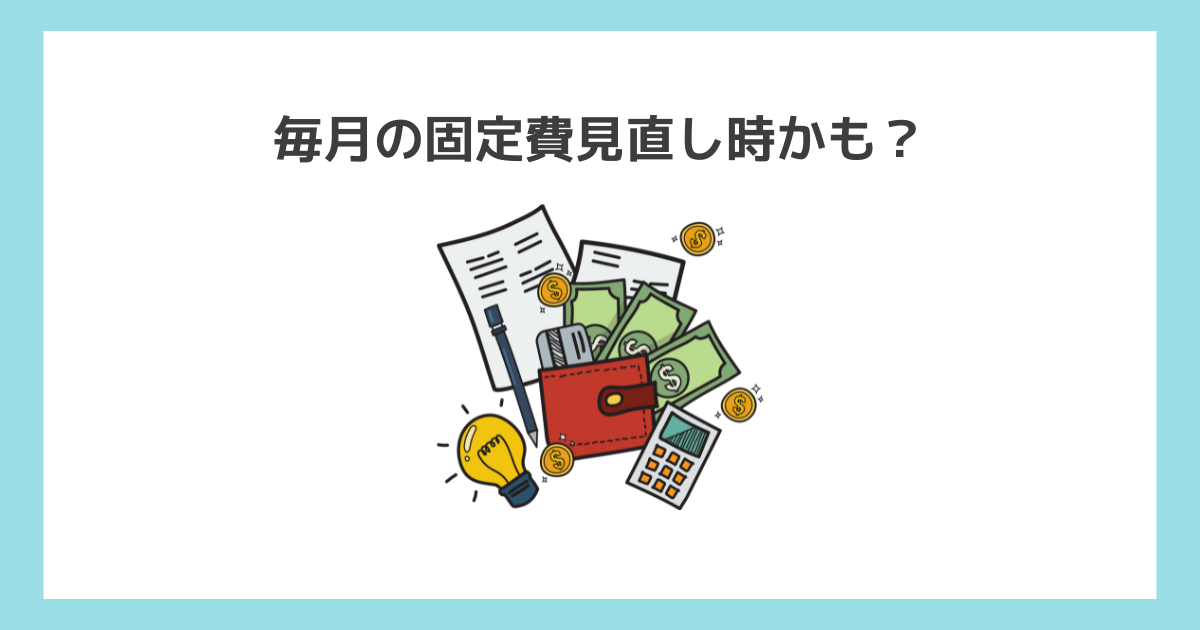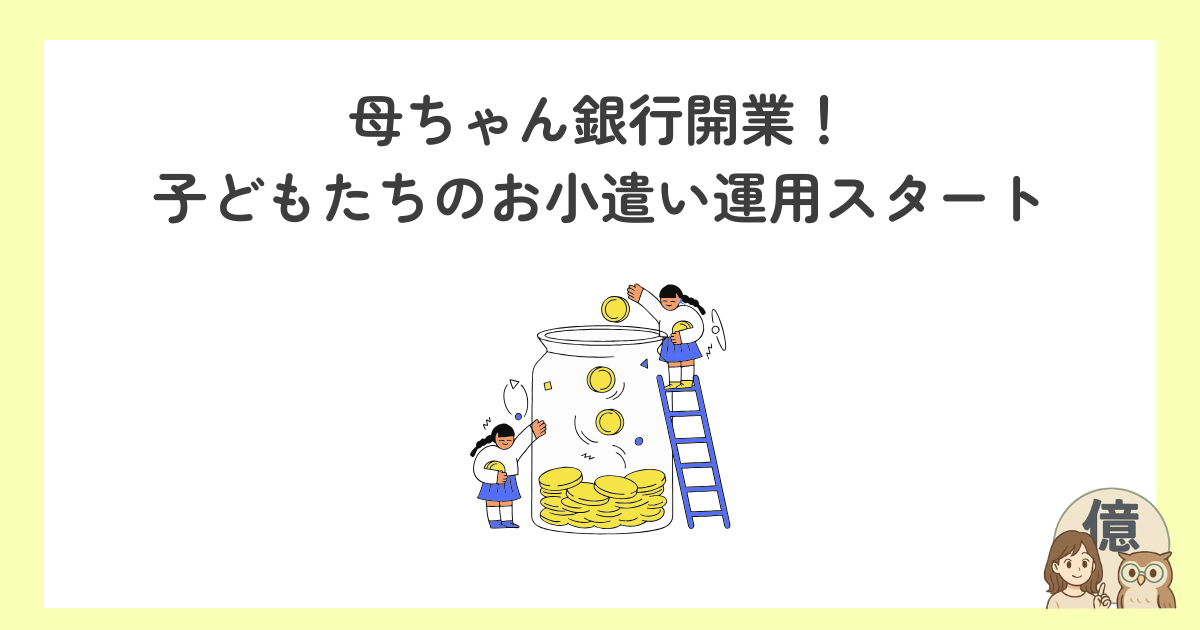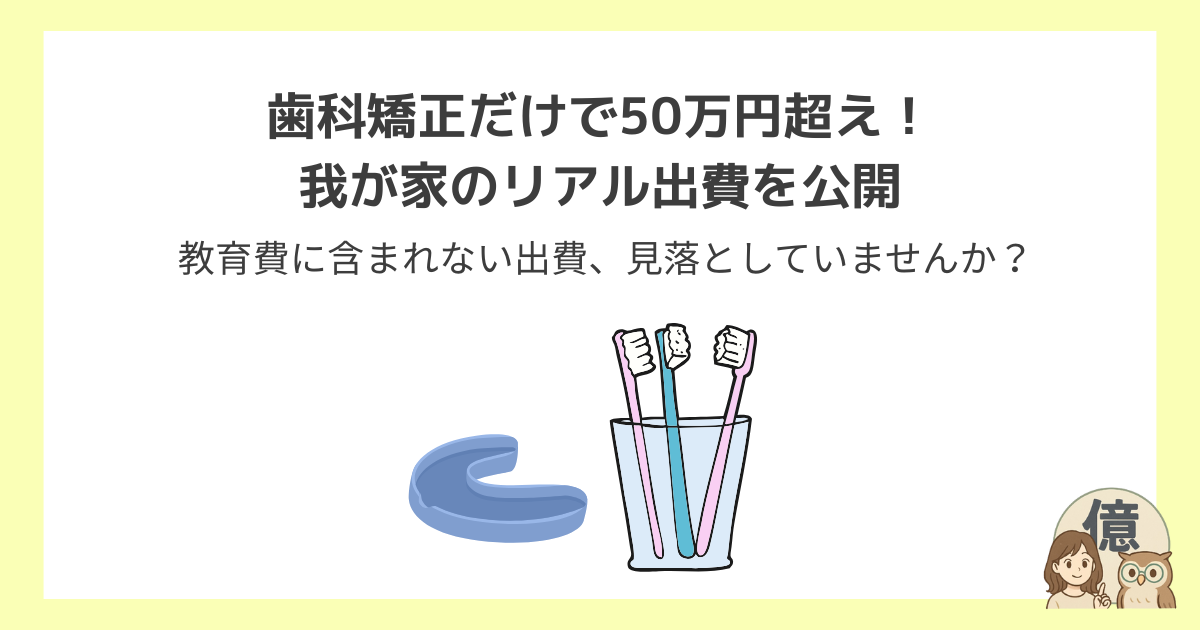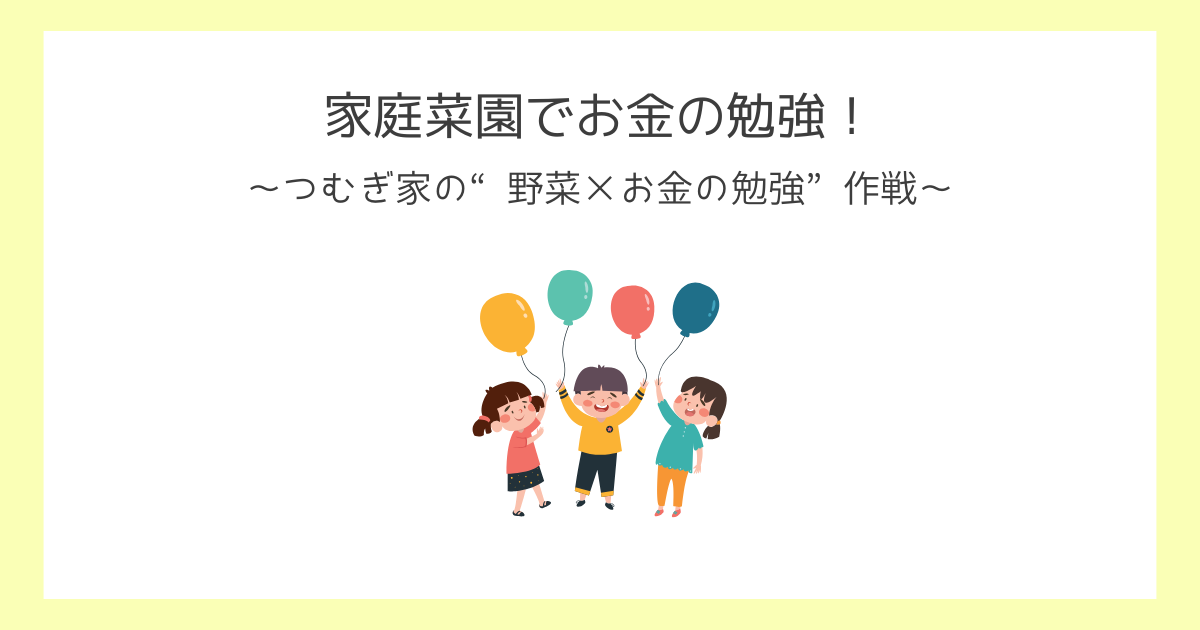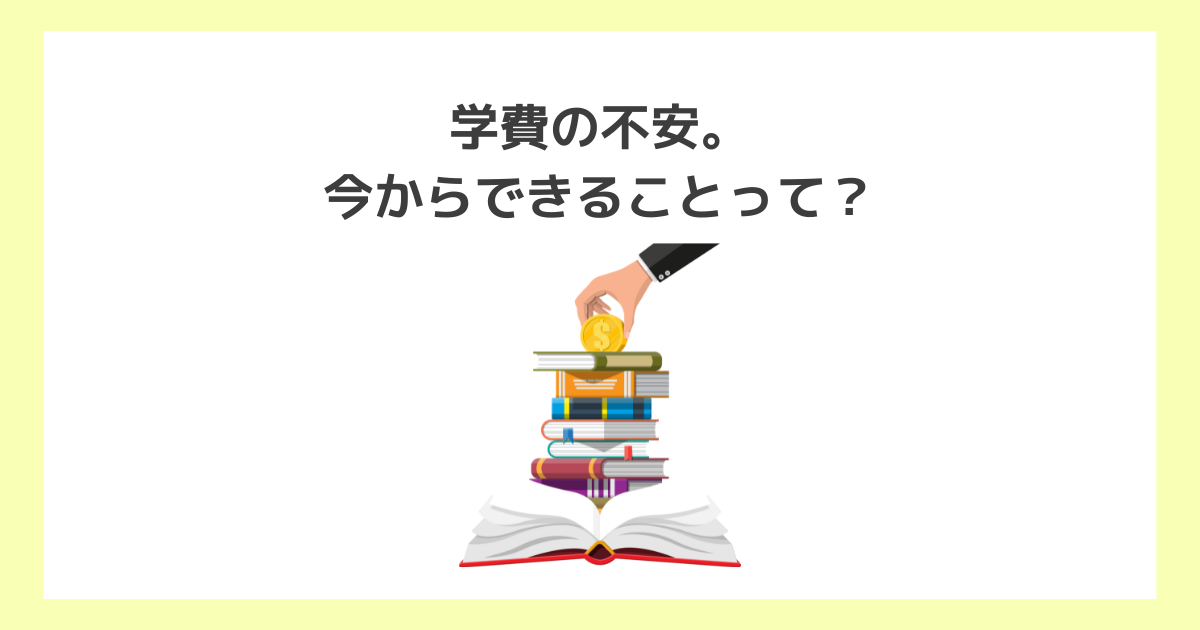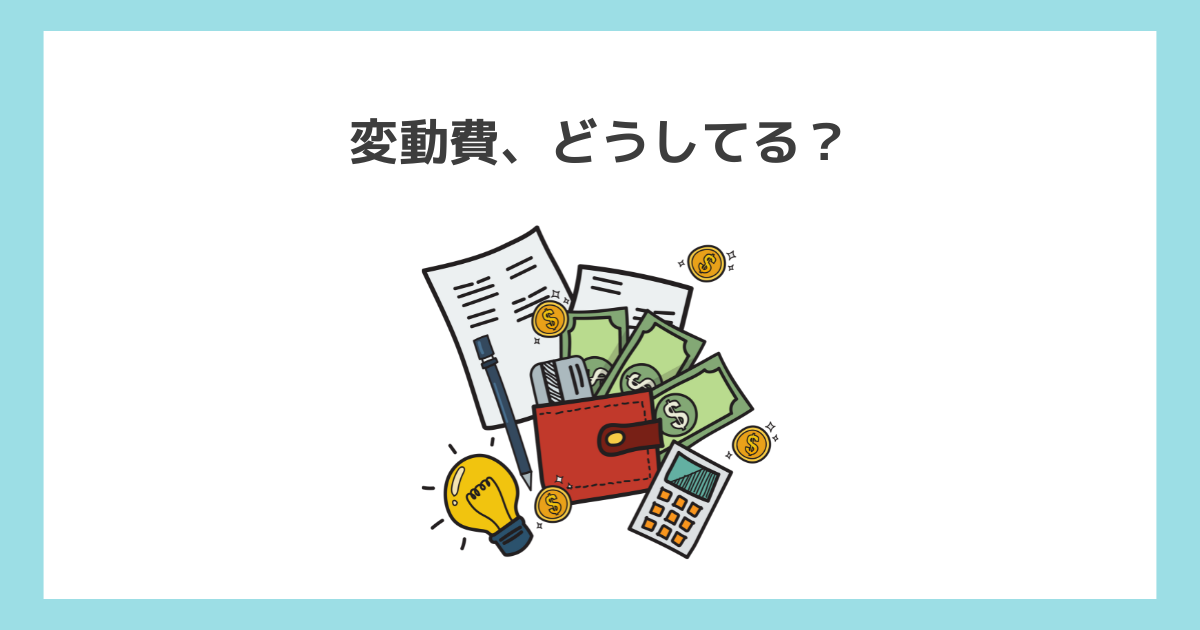「お小遣いっていつから?いくらあげればいい?」
そんな悩み、子育て中の家庭ではよく聞きます。
わが家にも小学生2人と保育園児1人がいますが、それぞれに年齢に応じた“わが家ルール”でお小遣いを渡しています。
この記事では、わが家のお小遣いの渡し方や金銭教育の工夫をご紹介します!
基本ルール|お小遣いは「年始のお年玉」から
まず、わが家のお小遣い制度のベースはこちら👇
- 小学生:月1,000円
- 保育園児:月500円
- 原資:年始のお年玉から1年分を先取り
お正月に親戚からいただくお年玉が、わが家ではお小遣いの予算になります。
そこから1年分のお小遣いを先に取り分け、
- 1ヶ月ごとに手渡し
- 残りは「証券口座 or 銀行口座」で管理
という方法で分けています。
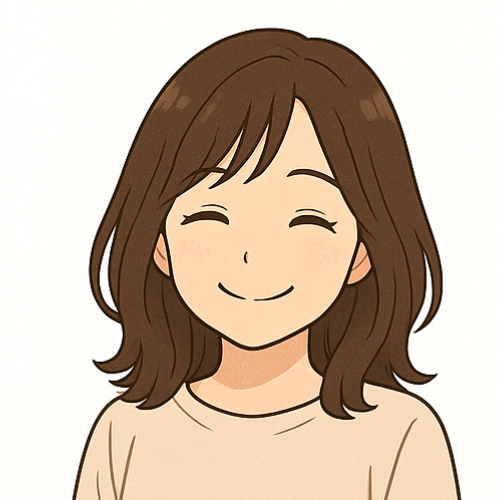
計画的に使う大切さを、自然と身につけてもらいたくて
初めての“お金の選択”|欲しいものは1つだけ
お年玉をもらったあとは、
「欲しいものを1つだけ選んで買ってOK」
というルールを設けています。
子どもたちは、
- どれにしようかな?
- 本当に今必要かな?
と、悩みに悩んで選ぶ姿が印象的です。
この「選ぶ・決める・責任を持つ」という経験が、金銭感覚の第一歩になると感じています。
お小遣いの使い道は自由|性格が出て面白い!
月々のお小遣いの使い道は基本的に自由にしています。
それぞれの特徴はこんな感じ👇
- 長男(小3):カードゲームが大好きで、ほとんどを趣味に投資
- 長女(小1):おやつを買ったり、ちょっとずつ貯金したり
- 次女(2歳):毎週のおやつ購入を楽しみにしている



お金の使い方にも、性格がよく出ますね
「なんでこれに使ったの?」と聞いてみると、ちゃんと自分なりの理由があるのも興味深いところです。
金銭教育のためのちょっとした工夫
お小遣いは、ただ「渡すだけ」ではなく、
- お金の出どころを説明する(お年玉から分けてるんだよ、など)
- お手伝いや努力と結びつけすぎない(労働報酬制は導入していません)
- 使ったあとの「気持ち」や「後悔」も一緒に振り返る
といった小さな工夫で、「お金=自分で管理するもの」と意識できるよう促しています。
📘“お金はツール”という考え方を伝えられたらいいなと思っています
まとめ|“金額”より“経験”を大切に
お小遣いって、金額の多さよりも**「どう使うか」「どう学ぶか」**が大切だと感じています。
わが家も試行錯誤しながら続けていますが、
- 欲しいものを我慢する力
- 自分のためにお金を使う楽しさ
- 必要と欲しいの違いに気づく
など、小さなお金の管理から大きな学びがあると実感しています。